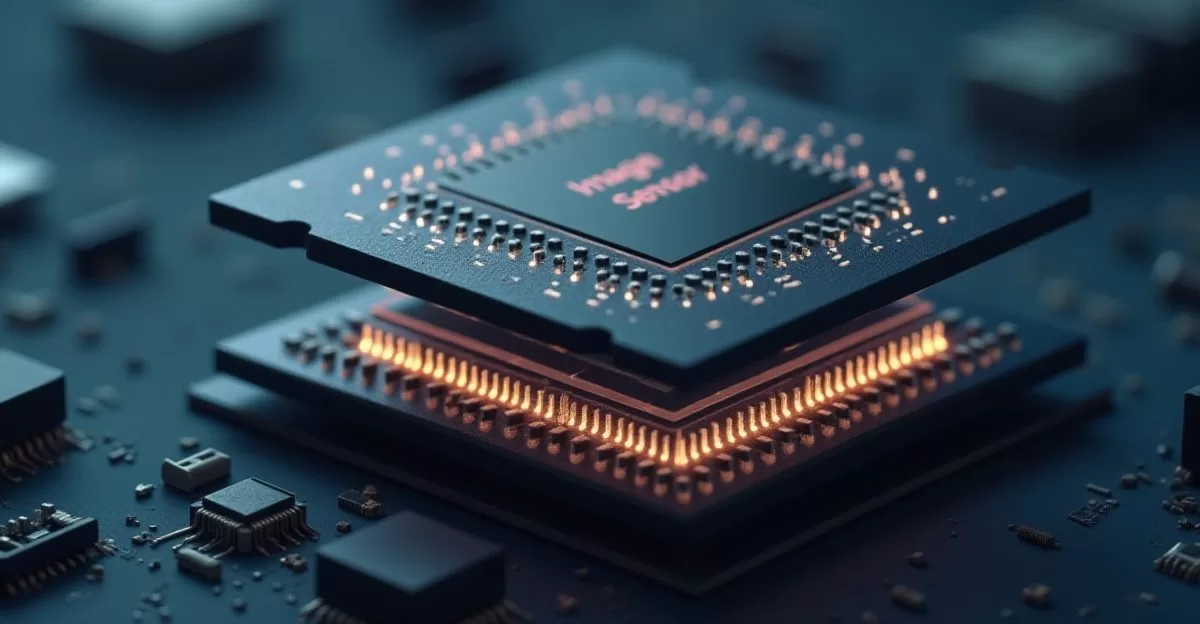半導体の世界では、いまもなお「最先端ノード=正義」という神話が強く残っている。
より微細に、より速く、より低消費電力に——その競争こそが技術進歩の象徴だと、多くの人は疑わない。
だが、その常識を少しだけ横に置いてみると、不思議な光景が見えてくる。
世界最高峰のイメージセンサーを量産し続けるソニーは、最先端の2nmや3nmではなく、28nmという一見「古い」プロセスを選び続けているのだ。
しかもその製造拠点は、日本に新設されたTSMC熊本工場。
最先端を追い求める拠点ではなく、「成熟したノード」を安定して量産するための場所として設計された工場である。
これは技術的な妥協なのだろうか。
それとも、コストの問題か。
あるいは、日本国内に工場を置くための政治的判断なのか。
本稿では、そうした表層的な説明から一歩踏み込み、
イメージセンサーという製品構造そのもの、
常時稼働を前提としたロジック層の現実、
そして量産・歩留まり・安定性という、現場レベルの制約からこの選択を読み解いていく。
結論を先取りすれば、ソニーの28nm選択は「最先端を避けた判断」ではない。
それはむしろ、最先端を知り尽くした上で選ばれた“最適解”であり、
TSMC熊本はそのために極めて合理的な役割を与えられている。
なぜ、最先端でなくてよいのか。
なぜ、28nmでなければならないのか。
そして、なぜそれが今も世界的に不足しているのか。
その理由を、順を追って見ていこう。
第1章|イメージセンサーは「1枚のチップ」ではない
スマートフォンやデジタルカメラに搭載されるイメージセンサーは、
しばしば「高精細」「高感度」といった言葉で語られる。
しかし、その中身がどのような構造で成立しているかまで意識されることは少ない。
現在、ソニーをはじめとする最先端のイメージセンサーは、
単一の半導体チップではなく、複数のチップを垂直に積み重ねた構造を採っている。
いわゆる「積層型CMOSイメージセンサー」だ。
この構造は、大きく2つの役割に分かれている。
- 画素層(Pixel Layer)
光を受け取り、電気信号へと変換する層。
ここは感度やノイズ特性が支配的で、ソニーが長年磨き上げてきた中核技術でもある。 - ロジック層(Logic Layer)
画素から流れ込む膨大な信号を処理し、デジタル化し、外部へ送り出す層。
画像処理、信号制御、読み出し速度などを担う、いわば「頭脳」に近い部分だ。
重要なのは、この2層が同じ条件を求めていないという点である。
画素層は、光学特性と物理構造が最優先される。
一方でロジック層は、計算能力・消費電力・発熱・歩留まりといった、
極めて“CPU的”な制約の中で設計される。
そしてこのロジック層こそが、
TSMC熊本工場が担う22nm〜28nmクラスのプロセスと、
極めて相性の良い領域なのである。
仮にロジック層だけを最先端の5nmや3nmで作ったとしても、
センサー全体の性能が飛躍的に向上するわけではない。
積層構造では、上下のチップは物理的な面積を揃える必要があり、
一方だけを極端に微細化しても、メリットは限定的だからだ。
むしろ、常時稼働するカメラモジュールにおいては、
発熱を抑え、安定した挙動を保ち、量産で確実に作れることのほうが重要になる。
ここで求められるのは、
「最も細いプロセス」ではなく、
最も扱いやすく、最も完成度の高いプロセスである。
この前提に立ったとき、
28nmという選択肢は、決して保守的でも後退的でもない。
それは、積層イメージセンサーという構造そのものが導いた、
極めて合理的な帰結だった。
第2章|ロジック層に「最先端」は本当に必要なのか
ロジック層は、イメージセンサーの中で最も「CPUに近い」存在だ。
画素から流れ込む信号を高速に処理し、ノイズを抑え、
フレーム単位で安定した出力を維持し続ける。
だからこそ、直感的にはこう思われがちだ。
──処理を担うのなら、より微細で、より高速なプロセスを使うべきではないか。
しかし、実際の設計現場では、この発想は必ずしも成立しない。
常時稼働という前提
スマートフォンのカメラや車載カメラは、
ベンチマークのために瞬間的に性能を引き上げる用途ではない。
撮影中は常に動き続け、動画では連続してフレームを処理し続ける。
このとき最も重要になるのは、
ピーク性能ではなく、発熱と消費電力の管理だ。
最先端プロセスは、微細化によって高い性能を得られる一方、
電流密度の増大やリーク電流の増加といった副作用を伴う。
短時間の処理なら問題にならなくても、
常時稼働するデバイスでは熱が蓄積しやすい。
結果として、クロックを下げる、回路を間引く、
といった制約が加わり、
理論性能ほどの差が実運用で出ないことも少なくない。
面積を揃える必要があるという現実
積層イメージセンサーでは、
画素層とロジック層は物理的に貼り合わされる。
このため、ロジック層だけを極端に微細化しても、
センサー全体のサイズは画素層に引きずられる。
チップ面積が劇的に小さくなるわけではない。
つまり、
「ロジックだけ最先端にすることで得られる恩恵」は、構造上限定的なのだ。
歩留まりと量産という壁
イメージセンサーは、
ハイエンドモデルだけでなく、
スマートフォン向けに膨大な数量が出荷される。
その前提にあるのが、
安定した歩留まりで、長期間にわたって量産できることである。
最先端プロセスは、
設計コストも製造コストも高く、
ラインの立ち上げや安定化にも時間がかかる。
製品ライフサイクルが長いセンサー分野では、
この不確実性は大きなリスクとなる。
一方、22nm〜28nm世代は、
設計手法も製造ノウハウも出尽くしており、
歩留まりが読みやすい。
ここで求められているのは、
「最も新しい技術」ではなく、
最も確実に量産できる技術だ。
“速い”よりも“安定している”こと
ロジック層が担う役割は、
派手な計算性能を見せることではない。
毎フレーム、同じ条件で、同じ処理を、確実にこなすこと。
この用途においては、
ブースト動作や複雑な電力制御を伴う最先端CPU的な振る舞いよりも、
挙動が予測でき、制御しやすい設計のほうが価値を持つ。
こうして条件を並べていくと、
28nmというプロセスが選ばれる理由は、
「妥協」ではなく「最適化」であることが見えてくる。
それは、ロジック層にとっての
現実解だった。
第3章|なぜ28nmなのか──“黄金ノード”と呼ばれる理由
28nmは、半導体の微細化の歴史において、
単なる「通過点」ではない。
それは、構造・コスト・性能のバランスが最も美しく成立した世代として、
今なお産業界で特別な位置を占めている。
プレーナ構造の完成形
28nmは、プレーナ型トランジスタ(平面構造)が主役として成立した
事実上の最終世代である。
これより先、16nm/14nm世代からは、
FinFETと呼ばれる立体構造が本格的に導入された。
微細化によるリーク電流の問題を抑えるための必然だったが、
その代償は大きい。
- 設計難易度の急上昇
- マスク枚数の増加
- 製造コストの跳ね上がり
- 立ち上げまでの時間の長期化
一方で28nmは、
- 構造が単純
- 設計資産が豊富
- 製造ノウハウが完全に出揃っている
という特徴を持つ。
これは「古い」からではない。
完成しているからだ。
コストと性能の“分岐点”
28nm世代は、
「そこそこの性能」を、
「非常に現実的なコスト」で実現できる。
これより微細なプロセスでは、
トランジスタあたりの性能向上は続くものの、
チップ1個あたりの総コストは必ずしも下がらない。
特に、
- 常時稼働
- 中程度の演算
- 高い信頼性
を求める用途では、
28nm以降で得られる性能向上は、コスト増に見合わない。
このため、車載、産業機器、通信、イメージセンサーといった分野では、
28nmが事実上の「最適点」として定着した。
“枯れた”ではなく“実証済み”
半導体業界では近年、
28nmクラスを単にレガシーとは呼ばない。
- Proven Node(実証済みノード)
- Long-tail Process(長期供給前提のプロセス)
といった表現が使われる。
これは、
設計・製造・運用のすべてにおいて、
想定外がほぼ残っていない世代であることを意味する。
製品寿命が10年単位に及ぶ分野にとって、
この「予測可能性」は、性能向上以上の価値を持つ。
世界的に不足する「不思議なノード」
直感に反して、
28nmはしばしば世界的に供給不足に陥る。
理由は単純だ。
- EV化で車載チップの需要が急増
- IoT・産業用途が拡大
- 国家戦略として28nmを確保しようとする動き
これらの需要が、
最も汎用性の高いこの世代に集中するからだ。
28nmは、
「余っている過去」ではなく、
奪い合われる現在に属している。
こうして見ていくと、
ソニーが28nmを選んだ理由は明確になる。
それは保守ではなく、
世界中の実需が収束した場所を選び取った結果だった。
第4章|TSMC熊本が担っている“現実的な役割”
TSMC熊本工場(JASM)は、
しばしば「最先端を作らない工場」として語られる。
しかし、実際にここで担われている役割は、
最先端か否かという軸では測れない。
JASMのプロセスが意味するもの
JASMが主力とするのは、
12nm〜28nmクラスの成熟プロセスだ。
これはスマートフォン向けのSoCや、
AI向けアクセラレータの最前線ではない。
だが同時に、
世界の産業を支える中心帯でもある。
- 車載マイコン
- 画像・センシング系ロジック
- 通信・制御用SoC
いずれも、
- 長期供給が必須
- 温度・振動など環境耐性が重要
- 性能よりも安定性が重視される
という共通点を持つ。
この条件に最も適合するのが、
28nm前後のProven Nodeだ。
ソニーにとってのTSMC熊本
ソニーがTSMC熊本に求めているのは、
「最新鋭の製造能力」ではない。
求めているのは、
- 自社工場では難しいロジック層の量産
- 高い歩留まり
- 安定した長期供給
という、極めて実務的な要件である。
イメージセンサーは、
製品寿命が長く、
同一設計を長期間作り続ける必要がある。
頻繁なプロセス移行や、
短命な最先端ノードは、
むしろ相性が悪い。
TSMC熊本は、
この「変わらないこと」を前提にした生産を担う場所として、
機能している。
デンソーと車載という文脈
同様の構図は、
デンソーをはじめとする車載分野にも当てはまる。
車載半導体は、
- 10年以上の供給保証
- 極端な温度変化への耐性
- 認証を含めた厳格な品質管理
が求められる。
一度認証されたプロセスを、
安定して作り続けられるかどうかが最重要だ。
この世界では、
「次の世代へ進むこと」よりも、
「同じ世代を続けること」のほうが難しい。
JASMは、
その“続ける力”を提供する工場だと言える。
「妥協」ではなく「役割分担」
TSMC熊本が最先端を担わないことは、
劣位を意味しない。
それは、
世界的な分業構造の中での役割分担だ。
- 最先端:短命・高コスト・高速進化
- 成熟ノード:長期・安定・大量実需
ソニーやデンソーが必要としているのは、
後者である。
TSMC熊本は、
その現実を最も正確に反映した工場として、
配置されている。
結語|“最先端でない”という選択が、最適解になるとき
半導体の世界では、
微細化の数字がしばしば技術力の象徴として語られる。
3nm、2nmといった言葉は、分かりやすく、刺激的だ。
だが、すべての製品が、
その競争に参加する必要はない。
イメージセンサーという分野において、
ソニーが選んだのは、
「最も新しいプロセス」ではなく、
最も完成度の高いプロセスだった。
積層構造、常時稼働、発熱制約、量産性、長期供給。
それらの条件を一つずつ積み上げていくと、
28nmという選択は、
自然な帰結として浮かび上がる。
TSMC熊本工場が担っているのも、
この現実的な要請に応える役割だ。
最先端を追う工場ではなく、
世界中の産業が必要とする“確実な半導体”を作り続ける場所。
ここにあるのは、
妥協でも後退でもない。
性能競争から降りる勇気と、
実需を見据えた冷静な判断。
それこそが、
“最先端でない最適解”という選択の正体だ。
数字だけを見れば、
28nmは過去に属するかもしれない。
だが、世界中の製品が今日もこの世代を必要としている以上、
それは現在進行形の技術であり続けている。
ソニーが28nmを選び、
TSMC熊本がその役割を担っているという事実は、
半導体における「進歩」とは何かを、
静かに問い直している。
進むとは、
必ずしも前へ行くことではない。
立ち止まるべき場所を、正しく選ぶこともまた、
技術の一つの成熟なのだ。