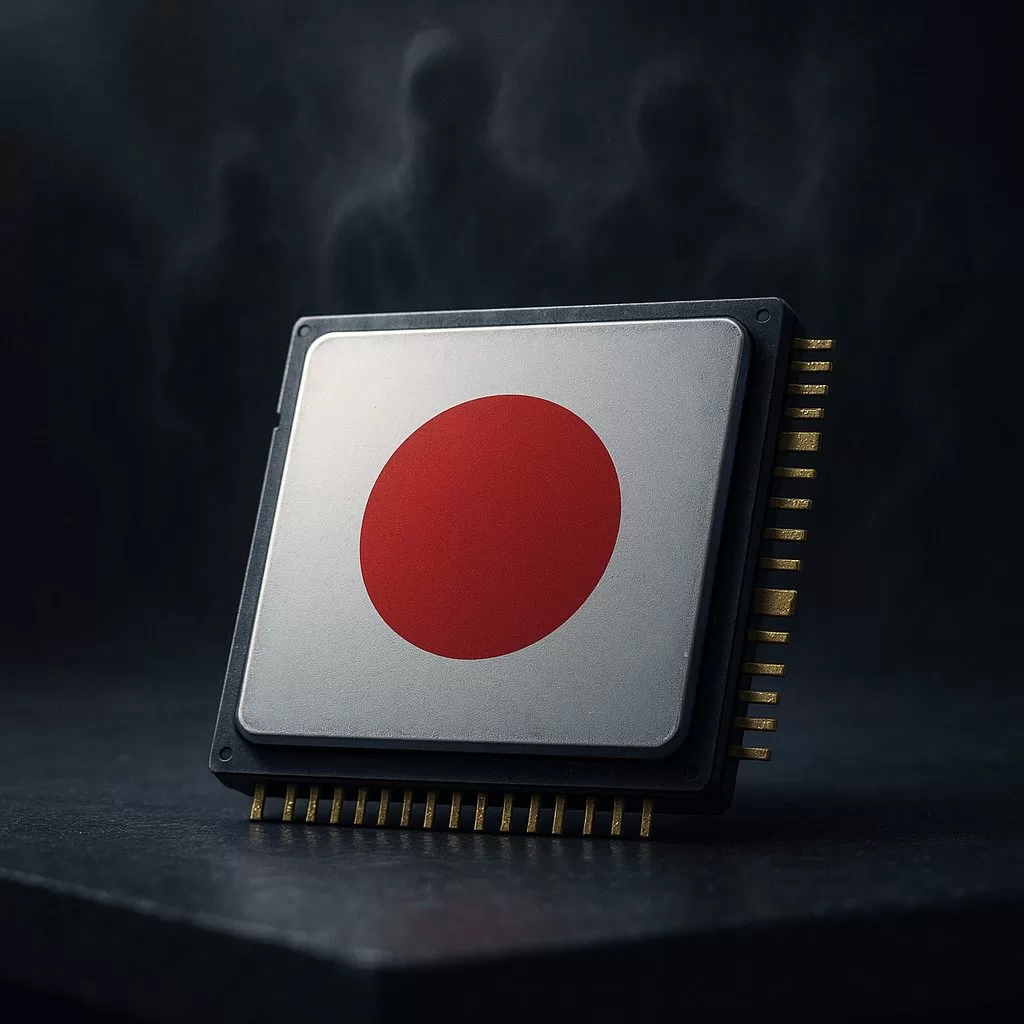かつて世界を席巻した「日の丸半導体」は、日米摩擦、過剰品質、投資不足、そしてエルピーダの破綻によって崩れ去った。
だがいま、日本は再び立ち上がろうとしている。北海道千歳に建設中のRapidusの2nm工場は、政府と産業界が総力を挙げた賭けだ。
自動車産業をはじめ、日本経済の屋台骨を支える分野は半導体なくして存続できない。復活は希望か、それとも再び亡霊に取り憑かれた幻想か──。
解体寸前の屋台骨
半導体は、もはやスマートフォンやPCのためだけの部品ではない。自動車、産業機械、エネルギー、通信──現代経済のあらゆる神経を走る基盤だ。
日本経済を支える自動車産業も例外ではない。EV化や自動運転技術の進展により、1台あたりに搭載される半導体の数は爆発的に増加している。もし供給が途絶すれば、トヨタもホンダも日産も、世界市場で戦う力を失う。
2020年代初頭の半導体不足では、そのリスクが現実となった。工場ラインが停止し、数兆円規模の損失が発生した事例は記憶に新しい。輸入依存が続けば、日本経済の屋台骨は揺らぎ続ける。
だからこそ「半導体の国産化」は避けられない課題だ。だが視野を「自国需要の確保」に狭めすぎれば、世界市場で存在感を示すことはできない。半導体産業は規模とスピードが命であり、台湾のTSMCや韓国のSamsungが築き上げた巨大なファウンドリ・エコシステムと伍するには、国家的覚悟と戦略が不可欠なのだ
昭和から平成へ ─ 栄光と凋落の系譜
1980年代、日本の半導体は「世界の王者」と呼ばれる地位にあった。DRAM市場ではシェア90%に迫り、アメリカ勢を蹴散らす勢いで成長した。高い品質と生産技術、そして銀行からの潤沢な資金供給が、世界市場を席巻する力となった。実際、Intelは日本勢の攻勢を受けてメモリ事業から撤退し、CPU専業へと転身する決断を迫られるほどだった。
だが、その栄光は長く続かなかった。1986年、日米半導体協定が結ばれる。米国の圧力によって価格規制や外資参入枠を受け入れ、日本企業は競争力を削がれた。さらに「品質至上主義」が裏目に出る。0.01%の欠陥すら許さない過剰品質はコストを押し上げ、利益を圧迫。大量生産・低コストを武器にする韓国・台湾勢との競争で不利を背負うことになった。
バブル崩壊後は投資余力を失い、半導体設備投資の継続性が途絶える。さらに、自前主義に固執して設計から製造、パッケージングまでをすべて自社内で抱え込み、業界の流れであった「ファウンドリー化」への移行に失敗した。台湾TSMCのように製造特化へ舵を切れなかったことは、日本半導体の致命傷となった。
そして追い打ちをかけたのが、人材の海外流出だった。国内での待遇や将来性に失望した技術者は、次々とアメリカ、韓国、台湾へ移籍。人材と投資の両輪を失った日本半導体は、平成の間に急速に存在感を失っていったのである。
エルピーダ ─ 復活の旗手が陥った罠
1999年、日本の半導体再生を託された新会社が誕生した。NEC、日立、そして後に三菱のDRAM部門を統合した「エルピーダメモリ」である。国策企業の色合いが濃く、「日の丸半導体」の再起を象徴する存在として大きな期待を背負った。
当初、エルピーダは技術力を武器に世界市場で一定の地位を築いた。高性能DRAMでサムスンに対抗し、PCやサーバー向けにシェアを拡大。しかし、半導体業界を覆う「価格競争の波」は容赦なく襲いかかる。韓国・台湾勢は巨額投資で量産効果を追求し、コストダウンを徹底。一方でエルピーダは、バブル崩壊後の日本らしく投資体力に乏しく、資金繰りに常に苦しんだ。
2008年のリーマンショックは、すでに疲弊していたエルピーダを直撃した。急激な需要縮小と円高による収益悪化で経営は急速に悪化。2012年、ついに会社更生法を申請し、経営破綻に追い込まれる。その後、エルピーダは米Micronに買収され、日本発のメモリ専業メーカーは歴史から姿を消した。
エルピーダの失敗は、単なる一企業の破綻ではなかった。そこには日本の半導体産業全体に共通する病理が映し出されていた。
- 投資不足
- ファウンドリー化への適応の遅れ
- 政策と現場の乖離
- グローバル市場での資金力・規模の欠如
「日の丸半導体」の再興を担うはずの旗手が倒れたことで、日本の半導体産業は名実ともに“空白の時代”に突入したのである。
その後の空白と半導体危機
エルピーダ破綻後、日本から最先端メモリメーカーは姿を消した。残されたのは製造装置や材料で世界シェアを持つ企業群と、汎用品を細々と供給するメーカーのみ。日本の半導体産業は、設計から製造、パッケージングまでを一気通貫で担う「総合力」を完全に失った。
その間に世界は急速に変化した。スマートフォンが普及し、クラウドサービスが急拡大、AIやEVといった新領域で半導体需要は爆発的に伸びた。しかし、日本にはそれを賄う生産基盤がなく、国内メーカーも多くは輸入に依存するしかなかった。
そして2020年代初頭、世界的な「半導体不足」が直撃する。パンデミックによるサプライチェーンの混乱、データセンター需要の急伸、そして自動車の半導体搭載量の急増が重なり、かつてない規模の需給逼迫が発生。国内自動車メーカーは生産ラインの停止を余儀なくされ、兆円単位の損失を計上した。
ここで改めて浮かび上がったのが「供給を海外に依存するリスク」である。台湾有事の可能性がささやかれ、TSMC依存の脆弱性が議論されるようになった。半導体が“戦略物資”であることを、日本はようやく痛感するに至ったのだ。
この「空白の10年」があったからこそ、Rapidusの挑戦は単なる産業政策ではなく、国家の安全保障と経済の存続をかけた賭け となったのである。
Rapidus ─ 国家プロジェクトとしての賭け
2022年、日本政府と大手企業連合が立ち上げた新会社──それが Rapidus(ラピダス) である。トヨタ、ソニー、ソフトバンク、NTTなど国内の錚々たる企業が出資し、さらに経産省が巨額の補助金を投入。設立から間もなく「国家的プロジェクト」としての色彩を帯びた。
Rapidusが掲げる目標はただ一つ。北海道・千歳に世界最先端の2nmプロセス対応ファブを建設し、2027年までに量産を開始すること。TSMCやSamsungと肩を並べるプロセス技術を、ゼロからわずか5年で立ち上げるという無謀とも思える挑戦だ。
技術支援と協業体制
Rapidusは孤立無援ではない。米IBM、ベルギーのIMECといった世界有数の研究機関と提携し、すでに100名を超える日本人エンジニアが米国で最先端技術の研修・共同開発に従事している。2024年には早くも試作チップの成功を発表し、技術的には前進を示している。
「品質優先」の生産方式
大手ファウンドリが効率重視で25枚単位のバッチ生産を行うのに対し、Rapidusは立ち上げ段階から1枚ずつ処理する方式を採用。量産効率では劣るが、歩留まり改善やトラブルシューティングのスピードで優位を取ろうとする姿勢だ。まさに「品質第一」「精度優先」という日本的アプローチが色濃く反映されている。
官僚の影と資金リスク
一方で不安要素も多い。国家主導であるがゆえに、官僚や政治の過剰な介入リスクは避けられない。補助金依存の経営は柔軟性を欠き、民間の俊敏さを損なう恐れがある。また、建設・設備投資・人材確保を合わせると必要資金は数兆円規模。政府支援が一時的に途絶すれば、エルピーダと同じ轍を踏みかねない。
Rapidusの挑戦は、産業再生策を超えた「国の存亡をかけた賭け」である。成功すれば日本は再び半導体大国として世界地図に復帰できる。だが失敗すれば、再び「亡霊」に取り憑かれたまま、歴史の教訓として葬り去られるだろう。
日本が持つ“地下資源” ─ 装置と材料の強み
日本は最先端ロジック半導体の量産競争からは脱落した。しかし、それで完全に存在感を失ったわけではない。むしろ半導体産業の“裏方”である製造装置と材料の分野において、日本企業は今なお世界のトップランナーとして君臨している。
製造装置:東京エレクトロンの存在感
半導体製造工程は、リソグラフィ、成膜、エッチング、洗浄といった数百の工程で構成される。その一つ一つを支える装置メーカーの代表格が 東京エレクトロン(TEL) だ。ASML(オランダ)が露光装置で独占的地位を持つのに対し、TELは成膜やエッチングなど周辺工程で圧倒的なシェアを誇る。世界の最先端ファブが稼働する限り、TELの装置なしでは成立しない。
材料:信越化学・SUMCOの独壇場
シリコンウエハや化学材料もまた、日本の牙城だ。信越化学工業 と SUMCO は、高純度シリコンウエハの世界シェアを大きく握っており、TSMCもSamsungも日本製ウエハを頼りにしている。またレジスト材、スラリー、各種薬品に至るまで、日本企業は供給の要となっている。
世界は日本に依存している
言い換えれば、日本は“半導体資源大国”なのである。石油やレアメタルのように、装置と材料は世界中のファウンドリが必要とする戦略物資。これらの分野で強みを持つ日本は、直接ロジックチップを作らなくとも、依然として世界の半導体産業を陰で支配しているとも言える。
しかし足りないもの
問題は、それだけでは世界の技術主導権を握れないという点だ。装置・材料に強みがあっても、最終製品のロジックチップを設計・量産する力がなければ、日本は「黒子」に留まる。Rapidusの挑戦は、この強大な裏方の力を表舞台へ引き上げる試みでもある。
Intelのファウンドリー失敗との対比
Rapidusの挑戦を語るうえで避けて通れないのが、アメリカの巨人 Intel の失敗である。
かつて「半導体の帝王」と呼ばれたIntelは、長年 IDM(設計から製造まで一貫する垂直統合モデル) にこだわり続けた。しかし、TSMCやSamsungがファウンドリー専業で急成長するなか、Intelは方向転換のタイミングを逸した。
ファウンドリー転換の遅れ
2010年代に入ると、Intelは先端プロセスで次々と歩留まり問題を起こし、10nm世代では量産が大幅に遅延。その間にTSMCは7nm、5nmと順調に世代を進め、AppleやNVIDIAなど主要顧客を総取りした。Intelは慌ててファウンドリー事業を立ち上げたが、既に市場の信頼を失っており、設計顧客を獲得できなかった。
IDMモデルの限界
自社製品(CPU)と外部顧客の製品を同じ工場で作る構造は、利害対立を生んだ。ファウンドリーとして他社を支援する姿勢が弱く、TSMCのような「顧客第一主義」のカルチャーを構築できなかったことが致命的だった。結果としてIntelのファウンドリー事業は赤字が続き、米国半導体戦略の“穴”とまで言われるようになった。
Rapidusへの示唆
この失敗から日本が学ぶべきことは明確だ。
- IDMへの固執を捨て、顧客と協業する体制を築くこと
- 単なる国産チップ供給にとどまらず、グローバル市場の需要を取り込むこと
- プロセス技術だけでなく、設計エコシステム全体を視野に入れること
もしRapidusが「国内需要確保」に閉じた戦略を取れば、Intelと同じ轍を踏む可能性がある。逆に言えば、顧客志向を徹底できれば、日本はIntelが落としたボールを拾い上げ、世界で存在感を取り戻すことができるかもしれない。
勝算とリスク ─ Rapidusの運命を左右する条件
Rapidusは「夢物語」と冷笑されることもあれば、「最後の希望」と期待されることもある。成功と失敗を分ける要因は何か。
勝算の根拠
- 品質文化と精密性
日本製造業のDNAである「カイゼン」と「品質至上主義」は、微細化が極限に達する半導体製造で武器になる。 - 装置・材料の国内基盤
東京エレクトロン、信越化学、SUMCOといった世界的企業の存在は、Rapidusにとって大きな後ろ盾。サプライチェーンの一部はすでに国内に揃っている。 - 政府の資金支援
数兆円規模の補助金が投入される点は、エルピーダ時代との最大の違い。資金面での安定感がある。 - 産業界の需要
EV、自動運転、データセンターといった分野で、国内大企業がRapidusの顧客候補になり得る。内需を確実に取り込みつつ、外需への展開も視野に入れられる。
リスクの要因
- 技術ギャップ
2nm世代の歩留まり改善は、経験の蓄積が必要。TSMCでさえ数年を要した領域を、Rapidusが短期間で埋められるかは未知数。 - 人材不足
半導体技術者の多くは海外へ流出し、国内には層が薄い。国外からの招聘が不可欠だが、報酬・環境整備に時間がかかる。 - 官僚主導のリスク
過剰な口出し、政策の揺れ、補助金頼みの体質は柔軟な経営判断を阻害する。エルピーダと同じ轍を踏む危険性は残る。 - コスト競争
TSMCやSamsungは規模の経済で圧倒的に優位。Rapidusが高コスト構造のままでは、量産段階でグローバル市場に食い込むのは難しい。
分岐点
Rapidusは「官製ベンチャー」という矛盾を抱えた存在だ。
成功するかどうかは、いかに迅速に民間の知恵と外部の顧客志向を取り込み、世界市場と接続できるか にかかっている。
もし国内市場だけを見て内向きになれば、エルピーダの亡霊が再び姿を現すだろう。
結語 ─ 亡霊を払う最後の賭け
日の丸半導体は、かつて世界の頂点に立ちながらも、エルピーダの崩壊に象徴されるように凋落の道を歩んだ。その背後には、日米摩擦に端を発する過剰品質、投資不足、技術者流出、自前主義の限界、そして官僚の硬直した政策があった。これらの「亡霊」は、いまなおRapidusの足元にまとわりついている。
だが同時に、日本には世界が羨む強みもある。半導体製造装置で世界トップを走る東京エレクトロン、シリコンウエハーで独占的地位を持つ信越化学・SUMCO。さらに精緻なものづくり文化と、顧客品質への徹底した執念。これらはRapidusの挑戦を支える土台である。
問われているのは「量」ではなく「存在感」だ。TSMCやSamsungを超える必要はない。だが、エルピーダのように再び幻に終わらせるわけにもいかない。自動車からAIまで、日本経済の屋台骨を揺るがす半導体不足に備え、最低限の独立した供給力を確保することが国家の命運を分ける。
Intelの失敗が示すのは、官民一体の総力戦でなければ勝てないという事実。そしてRapidusは、その総力戦に挑む最後の旗手である。成功すれば「亡霊」を振り払い、敗れれば再び長い暗闇に沈むだろう。
──日の丸半導体の復活は、過去への鎮魂であると同時に、未来への最後の賭けなのだ。