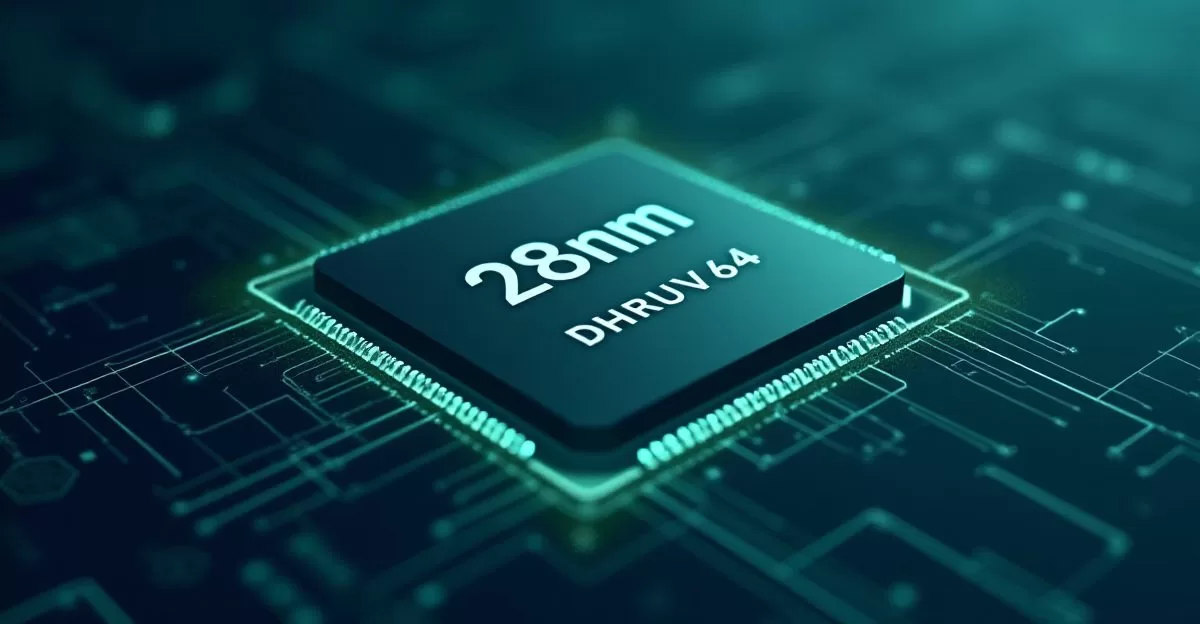半導体の歴史を振り返ると、
人類が最も重要な局面で信頼してきたのは、
必ずしも「最先端」のプロセスではなかった。
宇宙探査機、航空機、鉄道インフラ、車載制御、軍事システム。
これらの分野では、性能の高さよりも
「絶対に止まらないこと」、
「過酷な環境でも挙動が予測できること」が最優先されてきた。
その結果、数世代、時には数十年前の
いわゆるレガシープロセスが、あえて選ばれ続けている。
火星探査機に搭載されたPowerPC系CPUは1990年代の設計を基にし、
航空機の制御システムでは80286や80386の系譜が長く使われてきた。
鉄道や発電所の制御盤では、Z80や68000といったCPUが
現在も「現役」として稼働している。
それらは古いからではなく、
挙動が完全に理解され、長期供給が保証されているからだ。
最先端プロセスは、微細化と引き換えに
放射線耐性や長期安定性を失いやすい。
一方で、成熟したプロセスは
設計・検証・運用のすべてが出尽くしており、
「予測できる」という一点において圧倒的な強みを持つ。
こうした文脈に照らすと、
インドが発表したRISC-V CPU「DHRUV64」が
28nmというプロセスを選んだ理由は、
決して後ろ向きなものではない。
それは、性能競争からの撤退ではなく、
信頼を積み上げてきた技術史の延長線上にある選択だった。
第1章|28nmは本当に「遅れている」のか
「28nm」と聞いて、まず思い浮かぶのは
古い、遅れている、時代遅れ──そんな印象だろう。
スマートフォンやPC向けSoCの世界では、すでに2nmや3nmが語られる時代だ。
その文脈だけを切り取れば、28nmは10年以上前のプロセスである。
だが、産業界や国家インフラの視点に立つと、この評価は一変する。
28nmは、しばしば「レガシー」と一括りにされがちだが、
いわゆる「枯れすぎた技術」ではない。
車載、産業、IoT分野では現在も主流であり、
コスト、信頼性、供給期間のバランスが最も取れた
“実証済み(Proven Node)”として扱われている。
事実として、日本に建設されたTSMC熊本工場が採用しているのも28nmだ。
これは「最先端に追いつけなかった結果」ではない。
産業用途として、あえて選ばれたプロセスである。
28nmは、半導体製造において次のような特徴を持つ。
- EUV(極端紫外線)露光を必要としない
- 装置・材料・EDAツールが完全に成熟している
- 歩留まりが安定し、コストの見通しが立てやすい
- 10年単位の長期供給が現実的
これらは、消費者向けデバイスでは軽視されがちだが、
産業機器、車載、通信インフラ、防衛、宇宙分野では決定的に重要だ。
特に国家レベルのシステムでは、
「いま最速であること」よりも
「10年後も同じものを作り続けられること」が価値を持つ。
インドがDHRUV64で28nmを選んだ判断は、
技術的な妥協ではなく、用途と時間軸を正確に見据えた選択だと言える。
そしてこれは、インド固有の事情ではない。
日本を含む多くの国が、産業半導体の現場で
同じ現実と向き合っている。
28nmは、もはや「過去のプロセス」ではない。
主権と安定性を支える、現在進行形の選択肢なのである。
第2章|DHRUV64とは何か──1GHz・64bit・デュアルコアの意味
DHRUV64は、インドが国産で開発した
1.0GHz動作の64ビット・デュアルコアマイクロプロセッサである。
設計はC-DAC(先端コンピューティング開発センター)が担い、
国家プログラムの枠組みの中で開発・試作が行われた。
スペックだけを切り取れば、決して目新しいものではない。
1GHzというクロック、2コア構成、64ビット対応。
Arm系CPUで例えるなら、2013年前後に登場した
Cortex-A12クラスに近い水準だ。
時間軸で見れば、10年以上のビハインドがあることは否定できない。
だが、この比較は前提を誤っている。
DHRUV64は、スマートフォンやノートPC向けに
ベンチマークスコアを競うためのCPUではない。
設計段階から想定されている用途は、以下のような領域だ。
- 通信インフラ(5Gを含む)
- 産業オートメーション
- 車載システム
- 防衛・戦略用途
- 宇宙・衛星システム
- 組み込み・IoT分野
これらの分野では、
単純な演算性能よりも次の要素が重視される。
- 決まった処理を確実にこなすこと
- 長期間、同一仕様で運用できること
- 外部IPやライセンスに依存しないこと
- 自国で検証・改修・再設計が可能であること
DHRUV64の64ビット化は、
単にアドレス空間を拡張するためではない。
将来のソフトウェア資産、OS、ミドルウェアを
長期的に維持・発展させるための前提条件でもある。
また、デュアルコア構成は、
リアルタイム性とマルチタスクの両立を意識したものだ。
高クロック・多コア化ではなく、
制御しやすい並列性を選んでいる点が特徴的だ。
DHRUV64は「速いCPU」ではない。
しかしそれは、必要な速さを理解したCPUだと言える。
そしてこの設計思想こそが、
次章で触れる「性能を競わない、しかし性能を捨てたわけではない」
というインドの姿勢につながっていく。
第3章|性能を競わない、しかし“性能を捨てた”わけではない
DHRUV64を見て、
「インドは性能競争を放棄したのか」と感じる向きもあるだろう。
確かに、最先端プロセスや高クロック化を前面に押し出す設計ではない。
だが、それは性能を否定したのではなく、
性能競争の土俵を選び直した結果だ。
半導体の世界では、しばしば
「先端プロセス=高性能」という単純な図式が語られる。
しかし実際には、性能とは単一の指標ではない。
- 消費電力あたりの処理能力
- 熱設計の余裕
- リアルタイム性
- 長期安定動作
- 周辺IPとの統合効率
産業・インフラ用途では、これらが複合的に評価される。
DHRUV64が28nmを選んだのは、
「ここで性能を止める」という宣言ではない。
設計・製造・検証を国内で完結させるための第一段階に過ぎない。
実際、インド政府およびC-DACは、
次世代として14nmクラスへの移行を視野に入れた
Dhanush、Dhanush+プロセッサの開発を明言している。
この点は重要だ。
インドの戦略は
「最初から最先端に飛び込む」ことではなく、
「制御可能なプロセスで経験値を積み上げ、次へ進む」
という極めて現実的なものだ。
28nmで得られるのは、
単なるチップ1枚ではない。
- 設計フローの確立
- 検証・評価体制の内製化
- 人材の育成
- サプライチェーンの把握
- 製造ノウハウの蓄積
これらは、14nmやそれ以降のプロセスに進む際、
避けて通れない基盤となる。
言い換えれば、DHRUV64は
性能競争の前に、競争できる足場を固めるCPUなのだ。
先端プロセスを追いかけること自体は否定されていない。
否定されているのは、
足場のないまま最先端だけを欲しがる姿勢である。
この段階的なアプローチこそが、
次章で触れる「CPUを所有する」という国家的意味を
より現実的なものにしている。
第4章|CPUを「所有する」という国家的メリット
DHRUV64が持つ最大の価値は、
クロック周波数でもコア数でもない。
CPUを「所有している」ことそのものにある。
ここで言う「所有」とは、
単に国産である、という意味ではない。
- 命令セットを理解している
- 設計の中身を把握している
- 不具合を自分で検証・修正できる
- 必要であれば再設計できる
この状態にあることを指す。
多くの国や企業が使っているプロセッサは、
外部ベンダーのブラックボックスに依存している。
仕様書はあっても、設計思想や内部構造のすべてを
把握できるわけではない。
通常はそれで問題ない。
だが、防衛、宇宙、通信インフラ、重要産業となると話は別だ。
- 想定外の挙動が起きたとき
- セキュリティ上の懸念が生じたとき
- ライセンス条件が変わったとき
- 国際情勢によって供給が不安定になったとき
こうした局面で、
「自分たちで触れないCPU」は一気に弱点になる。
RISC-Vを採用したDHRUV64は、
命令セットレベルから設計を掌握できる。
これは、ソフトウェアだけでなく、
ハードウェアの振る舞いそのものを
自国で検証できることを意味する。
また、28nmという成熟プロセスの採用は、
この「所有」を現実のものにする上で重要な要素だ。
先端プロセスでは、
製造条件や歩留まり、マスク修正の一つひとつが
巨大なコストと外部依存を伴う。
結果として、設計を「理解していても触れない」状態に陥りやすい。
一方、成熟したプロセスであれば、
試作、改修、再評価を繰り返すことができる。
CPUを“使う”のではなく、
育てるという選択が可能になる。
DHRUV64は、
インドにとって最速のCPUではない。
だが、最も自分たちの手の内にあるCPUだ。
この差は、平時には見えにくい。
しかし有事や長期運用の局面で、
決定的な違いとなって現れる。
そしてこの「所有」という考え方が、
次章で触れる
なぜRISC-Vだったのか
という問いへの答えにつながっていく。
第5章|なぜRISC-Vだったのか──Armでもx86でもない理由
DHRUV64を語る上で、
避けて通れない問いがある。
なぜRISC-Vだったのか、という点だ。
選択肢は他にもあったはずだ。
Arm、あるいはx86。
どちらも実績があり、エコシステムも成熟している。
しかし、インドはそのどちらも選ばなかった。
まずx86については、現実的な選択肢ではない。
命令セット、設計、実装のすべてが
IntelとAMDという二社に強く集中しており、
新規参入や自立的な展開はほぼ不可能だ。
仮に技術的に可能だったとしても、
ライセンス、供給、政治的制約を含めた
リスクは極めて大きい。
Armはどうか。
Armアーキテクチャは広く普及しており、
技術的にも洗練されている。
だが、そこには常にライセンスという前提がある。
- 命令セットの使用条件
- コア設計の利用範囲
- 契約内容の変更リスク
- 国際情勢による影響
平時であれば問題にならないことも、
国家インフラや防衛用途では
長期的な不確実性として残り続ける。
この点で、RISC-Vは性質がまったく異なる。
RISC-Vは、
命令セットそのものがオープンであり、
ライセンス費用を必要としない。
設計の自由度が高く、
自国の用途に合わせた拡張や最適化が可能だ。
だが、重要なのは
「無料だから」という理由ではない。
RISC-Vは、
思想と設計文化を含めて導入できるアーキテクチャである。
- 命令セットをどう定義するか
- どこまでを共通化し、どこを独自化するか
- 人材をどう育て、どう継承するか
こうした判断を、
自国の裁量で行うことができる。
インドが進めているDIR-V(Digital India RISC-V)プログラムは、
単なるCPU開発ではない。
学界、産業界、スタートアップを巻き込みながら、
共通の設計基盤を国内に根付かせる試みだ。
これは、Armやx86を「使う」立場では
決して得られない経験である。
RISC-Vを選ぶということは、
性能表の数字ではなく、
設計主権を優先するという意思表示だ。
そしてこの選択は、
インド一国に限った話ではない。
次章では、
中国、インド、日本という三者が、
なぜ同じ「28nm」という地点で交差しているのかを見ていく。
第6章|中国、インド、日本──28nmが交差する地点
DHRUV64の28nm採用は、
インド固有の事情だけで説明できるものではない。
視点を広げると、中国、そして日本もまた、
同じ地点に立っていることが見えてくる。
中国は長年、半導体の自立を国家目標として掲げてきた。
その過程で、Armアーキテクチャを積極的に採用し、
一部ではx86互換にも色気を見せてきた。
だが現実には、
先端プロセス、EDAツール、製造装置、ライセンスの多くが
国際的な制約の影響を受ける。
特に最先端ノードに近づくほど、
外部依存はむしろ強まる。
その結果、中国のスマートフォンや組み込み分野では、
RISC-Vへの移行が着実に進みつつある。
これは「思想的な選択」というより、
制御可能な技術を選ばざるを得ない現実の帰結だ。
一方、日本を見てみるとどうか。
TSMC熊本工場が担うのは、
3nmや2nmといった最先端プロセスではない。
主力は28nmを中心とした成熟ノードだ。
これは、日本の半導体産業が
最先端競争から撤退したことを意味しない。
むしろ、産業・車載・制御分野において
長期供給と品質を最優先する現実的判断と言える。
つまり、中国、インド、日本はいずれも、
「最先端ではないが、確実に制御できるプロセス」
という一点で交差している。
28nmは、
もはや過去の遺産ではない。
地政学、産業構造、供給網の制約を踏まえた上で、
各国が選び取った現実解だ。
そして、この交差点にRISC-Vという
オープンな命令セットが重なったとき、
CPUは単なる部品から
国家戦略の構成要素へと姿を変える。
DHRUV64は、その象徴的な事例だ。
次章では、ここまでの議論を踏まえ、
本稿全体を静かにまとめていく。
第7章|DHRUV64が示したのは「先端を捨てる勇気」ではなく「順序を守る覚悟」
DHRUV64は、
最速でも、最先端でもない。
だが、それは欠点ではない。
インドが選んだのは、
性能競争からの撤退ではなく、
競争に参加するための順序を守ることだった。
まずは28nmという成熟プロセスで、
設計・検証・製造・人材育成を自国の手に取り戻す。
その上で、14nm、そして次の世代へと進む。
この段階的なアプローチは、
遠回りに見えて、実は最も堅実だ。
CPUを所有するとは、
速さを誇ることではない。
直せること、続けられること、育てられることだ。
DHRUV64は、
そのための足場として設計されたプロセッサである。
28nmの逆襲とは、
過去への回帰ではない。
現実を見据えた前進だ。
そしてこの現実は、
インドだけのものではない。
日本を含む多くの国が、
すでに同じ問いの前に立っている。
どのプロセスを選ぶのか。
どのアーキテクチャを使うのか。
そして、どこまでを自分たちの手で握るのか。
DHRUV64は、その問いに対する
一つの静かな答えを示している。