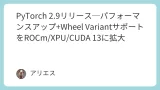CUDAが作った帝国
2006年、NVIDIAが発表した「CUDA」は、当時まだ“グラフィックス描画専用”と見なされていたGPUの世界を根底から変えた。
CUDAは「GPUを汎用計算に使う」ためのプログラミング環境であり、エンジニアがC言語ライクなコードを書くだけで並列演算を呼び出せる仕組みを提供した。その結果、GPUは単なる3D描画装置から、科学計算・機械学習・暗号通貨マイニングまでを支える 汎用コンピューティング基盤 へと躍進したのである。
CUDAの真価は単なるAPIの提供にとどまらない。
cuDNN(ディープラーニング用ライブラリ)、NCCL(分散通信ライブラリ)、TensorRT(推論最適化基盤)といったソフトウェア群が次々と追加され、研究者から産業界まで「CUDAで動かせば間違いない」という共通認識を形成した。これは単なる技術ではなく、プラットフォーム支配の論理そのものだった。
やがて2010年代、ディープラーニングのブレイクスルーとともにCUDAは揺るぎない地位を固める。ImageNetを制したAlexNetも、AlphaGoも、ChatGPTに至る巨大モデルも、その背後にはCUDA最適化されたGPUクラスタがあった。いまやAI研究のフロントラインにおいて、CUDAは 事実上の標準語 となり、NVIDIAは半導体企業を超えて「AIインフラの覇者」へと成り上がったのである。
──
だが、栄華の影には常に不満も積み重なる。
GPUの価格高騰、NVIDIA依存の開発環境、そして競合規格の不発…。
この「帝国」を揺さぶろうとした挑戦者たちは数多く現れたが、その試みはことごとく潰えた。
次章では、その“不発の象徴”とも言えるVulkanやOpenCLの敗北を振り返りながら、なぜCUDA帝国がこれほどまでに強固だったのかを見ていく。
CUDA一強に対する不満
CUDAが築いた帝国は、技術的に見れば驚異的な成功だった。
だがその支配力が強固であればあるほど、産業界のフラストレーションもまた大きくなっていった。
まず突き刺さったのは 価格の高騰 である。
ディープラーニング需要の急増に伴い、ハイエンドGPUは数百万円規模に跳ね上がり、研究室や中小企業にとって手の届かない存在となった。クラウド事業者もまた、NVIDIAへの依存を強めるごとに調達コストと供給リスクに頭を抱えることになる。
次に問題となったのは 技術的依存 だ。
CUDAは利便性が高い反面、エコシステムごとNVIDIAに囲い込まれる。
「CUDAでしか使えない最適化」「CUDA前提で動くライブラリ」──こうした縛りが積み重なり、結果として GPU計算=CUDA計算 という図式が出来上がった。開発者は学習コストを一度負担すれば効率的に成果を得られるが、その代償としてNVIDIA以外の選択肢を事実上失うことになった。
さらに、競合規格の存在もかえって不満を募らせた。
「オープン規格だから安心」と期待されたOpenCLは、移植性を優先するあまりパフォーマンスが伸びず、Stable DiffusionをOpenCLで動かした事例に象徴されるように「理論上は動くが、実用には程遠い」結果となった。Vulkan Computeも登場したが、開発環境の整備が遅れ、CUDAに比べて魅力を発揮できなかった。
こうして、産業界は 「NVIDIAの一人勝ちに従うしかない」 状況に追い込まれた。
その一方でクラウド大手は独自チップ路線に走り、TPUやTrainiumといった専用アクセラレータを次々と打ち出す。だがそれもまたソフトウェアエコシステムの壁に阻まれ、CUDAを揺るがすには至らなかった。
──
CUDA帝国を揺さぶろうとした挑戦は、ことごとく壁に跳ね返された。
だが、2025年──新たな刺客が現れる。
それが ROCm7 である。
Vulkanの敗北と雪辱
CUDA帝国に対抗するため、業界は「オープン規格」という武器を掲げた。
その代表格が OpenCL であり、後に登場した Vulkan Compute であった。理念は明快だ──「ベンダーを問わず、どのGPUでも同じコードが動く」。
まさに産業界が求めていた“自由の旗印”だった。
しかし、現実は無残である。
OpenCLは互換性を優先した結果、ハードウェアの特性を活かした最適化が難しく、性能はCUDAに遠く及ばなかった。Stable DiffusionをOpenCL実装で動かした事例では「動くことは動くが、CUDA版の数分の一の速度」という惨状が広く共有された。**「オープンだからこそ遅い」**という逆説的な状況が、開発者の心を冷やしてしまったのである。
Vulkan Computeもまた、期待を背負って登場したが、状況を覆すには至らなかった。
グラフィックスAPIとしては高い評価を得たものの、HPCやAI分野で使うには開発環境やライブラリが整わず、CUDAとのギャップは埋まらなかった。結局、「CUDAでやればすぐ動く」「ドライバも安定している」という利便性の前に、オープン規格は霞んでしまった。
この挫折は業界に深い教訓を残した。
「理念だけでは帝国は揺るがない」。
速度、安定性、そして開発者を惹きつけるライブラリ群──その総合力がなければ、いかに旗印を掲げても形勢を逆転することはできない。
──
だが、ここで終わりではなかった。
VulkanやOpenCLの敗北は、単なる挫折ではなく「次なる挑戦」の布石でもあった。
その挑戦者こそ、CUDA互換を掲げて現れた ROCm7 である。
ROCm7の登場
2025年、AMDはついに本命を繰り出した。
それが ROCm7(Radeon Open Compute 7)である。
従来のROCmは「HIPを使えばCUDAコードを移植できます」という姿勢にとどまっていた。だがROCm7では戦略を大きく転換し、CUDA互換レイヤーを打ち出したのである。
これは単なる小手先の改善ではない。
CUDAコードをほぼそのままAMD GPUで動かせるというのは、長年業界が待ち望んでいた“橋”だった。PyTorchやTensorFlowといった基盤はもちろん、vLLMやSGlangのような新興推論エンジンまで、CUDA依存のソフトウェアが「そのまま」動く可能性を開いたのである。
しかもROCm7は、互換性だけでなく 低精度演算のネイティブサポート という切り札を携えていた。FP8、さらにはFP4といった極めて低精度の演算をハードウェアレベルで処理できることは、推論コストを劇的に削減する可能性を秘めている。クラウド事業者にとって、電力効率の改善はそのまま利益率に直結する。AMDが「安く、速く、同じコードで動く」GPUを提供できるなら、NVIDIA一強体制に風穴を開けられる。
もちろん、課題も少なくない。
CUDAは20年近い歴史の中で最適化と検証を積み上げてきた。ROCm7が掲げる互換性が「ベンチマークでは動いたが、実際の大規模運用では不安定だった」となれば、開発者の信頼を失う危険は大きい。産業界は“第二のOpenCL”を望んでいるわけではないのだ。
──
それでもなお、ROCm7の登場は歴史的な転換点である。
CUDA帝国の城壁を真正面から揺さぶる存在が現れたのは、これが初めてだ。
次章では、この逆襲の切り札── FP8/FP4による低精度戦争 を詳しく見ていく。
低精度演算の勝負(FP8/FP4)
AI計算において、精度は常にコストとトレードオフの関係にある。
研究初期のディープラーニングは32ビット浮動小数点(FP32)が主流だったが、やがて16ビット(FP16)で十分な学習が可能だと判明し、GPUの演算効率は飛躍的に向上した。いま注目されているのは、さらに低い FP8、さらには FP4 という精度である。
精度を落としても意味はあるのか?
驚くことに、多くのAIモデルは推論フェーズにおいて必ずしも高い数値精度を必要としない。
学習で獲得したパラメータをもとに推論を行う際、8ビットや4ビットへの量子化でも十分に近い精度が維持できることが次々と報告されている。むしろ、低精度化によってメモリ帯域や電力消費が抑えられ、推論速度は大幅に向上する。
NVIDIAの先手、AMDの逆襲
NVIDIAももちろんFP8対応を打ち出しているが、その多くは「ソフトウェアによる近似演算」であり、真にハードウェアでネイティブ処理しているわけではない。
一方でAMDは、最新GPUで FP8/FP4をハードウェアレベルでネイティブ対応 すると宣言した。これは単なるマーケティング用の仕様ではなく、「同じ電力でより多くの演算をこなす」という現場ニーズに直結する。
産業界にとっての意味
AI推論は今後、学習以上に圧倒的な需要を生むと予測されている。
スマートフォンからクラウドまで、あらゆる領域でAIが常時動作する時代において、電力効率は事業採算そのものを左右する。FP8/FP4の低精度演算が安定して利用可能になれば、クラウド事業者にとって コスト削減=競争力の源泉 となる。
——
精度を落として効率を上げる。
この逆説を武器に、AMDはNVIDIAの牙城に迫ろうとしている。
次章では、この技術的切り札が産業界にどう受け止められ、どのような期待と懐疑を呼んでいるのかを見ていこう。
産業界の期待と懐疑
ROCm7とFP8/FP4の登場は、産業界に確かな衝撃を与えた。
特にクラウドベンダーにとって、これは久々に 「NVIDIA以外の現実的な選択肢」 が出現した瞬間である。
期待の理由
- コスト構造の改善
GPUサーバーの電力コストは膨大であり、FP8/FP4による効率化は直接利益に跳ね返る。 - 供給の多様化
これまでNVIDIAが握っていた供給網にAMDが割り込めば、価格交渉力が高まる。 - ソフト互換性
CUDA互換レイヤーが本当に機能すれば、既存の膨大なコード資産を再利用できる。これは専用チップ群にはなかった利点である。
それでも残る懐疑
だが同時に、多くの企業は慎重な姿勢を崩していない。
- 互換性の完全性
CUDA互換をうたっても、微妙な挙動差や非対応APIが出る可能性がある。大規模システムでは“1%の非互換”が全体を止める。 - エコシステムの厚み
NVIDIAには20年積み上げたライブラリ、ツール群、開発者コミュニティがある。AMDが短期間で同じ厚みを築けるのかは未知数だ。 - 実運用での信頼性
研究室レベルのベンチマークではなく、数万GPU規模のクラスタで安定稼働できるかどうか。ここが最大の関門である。
専用チップとの比較
さらに産業界は、Google TPUやAWS Trainiumといった専用チップ群との天秤にかけてAMDを見ている。
専用チップは理論上の効率は高いが、開発者にとって「既存コードがそのまま動く」利点は薄い。
ROCm7はこの両者の間に立ち、「CUDA並みの互換性 × 専用チップ級の効率」 を実現できるかが評価の分かれ目となる。
——
産業界は期待と懐疑の間で揺れている。
だが一つだけ確かなことがある──CUDA帝国に初めて本格的な挑戦者が現れた という事実だ。
次章では、いよいよ未来展望として「CUDA帝国の揺らぎ」と「GPU戦国時代」の行方を見据えていこう。
未来展望:CUDA帝国の揺らぎ
長らく「GPU=CUDA」の等式は揺るがない常識とされてきた。
しかしROCm7の登場は、その常識に亀裂を入れた最初の槌音となった。
NVIDIAが迎える調整局面
NVIDIAの強みは単なるハードウェア性能ではなく、20年かけて築いた エコシステムの総合力 にある。
cuDNNやTensorRTは今後も不可欠であり、CUDA帝国は一朝一夕には崩れない。
だが、供給制約や価格の高さが続けば、クラウドベンダーや研究機関は現実的な代替策を模索せざるを得ない。ROCm7がその候補として台頭すれば、NVIDIAも従来の強気な戦略を調整せざるを得なくなるだろう。
GPUと専用チップのせめぎ合い
この数年、TPUやTrainiumなど専用チップが台頭した背景には、「NVIDIA以外に選択肢がない」という不満があった。
もしAMDが互換性と効率性を両立できれば、産業界は再び 汎用GPU路線 に回帰する可能性がある。専用チップの役割は一部のニッチに縮小し、再び「GPU戦国時代」とも呼ぶべき群雄割拠が訪れるかもしれない。
歴史は繰り返す
計算機史を振り返れば、専用機と汎用機の波は繰り返されてきた。
ベクトル計算機からGRAPE、そしてCUDAによる汎用化、今また専用化の波が押し寄せている。
その流れに抗うかのように、ROCm7は「専用化の逆風に挑む汎用GPUの逆襲」として登場したのだ。
GPU戦国時代へ
未来は一つではない。
量子コンピューティング、光学演算、ニューロモルフィック──新しい計算パラダイムが次々と現れる中で、GPUの役割は再定義され続けるだろう。
だが少なくとも今後10年、AIインフラの主戦場は依然としてGPUにある。
そしてその覇権をめぐる戦いは、CUDA帝国の調整局面 × ROCm7の逆襲 × 専用チップの台頭 という三つ巴の構図で展開される。
——
CUDAが築いた帝国に、ついに攻城兵器が現れた。
それがROCm7である。
この挑戦が「一過性の反乱」に終わるのか、それとも「新たな戦国時代の幕開け」となるのか──2025年以降の計算機史は、その答えを我々に示していくだろう。