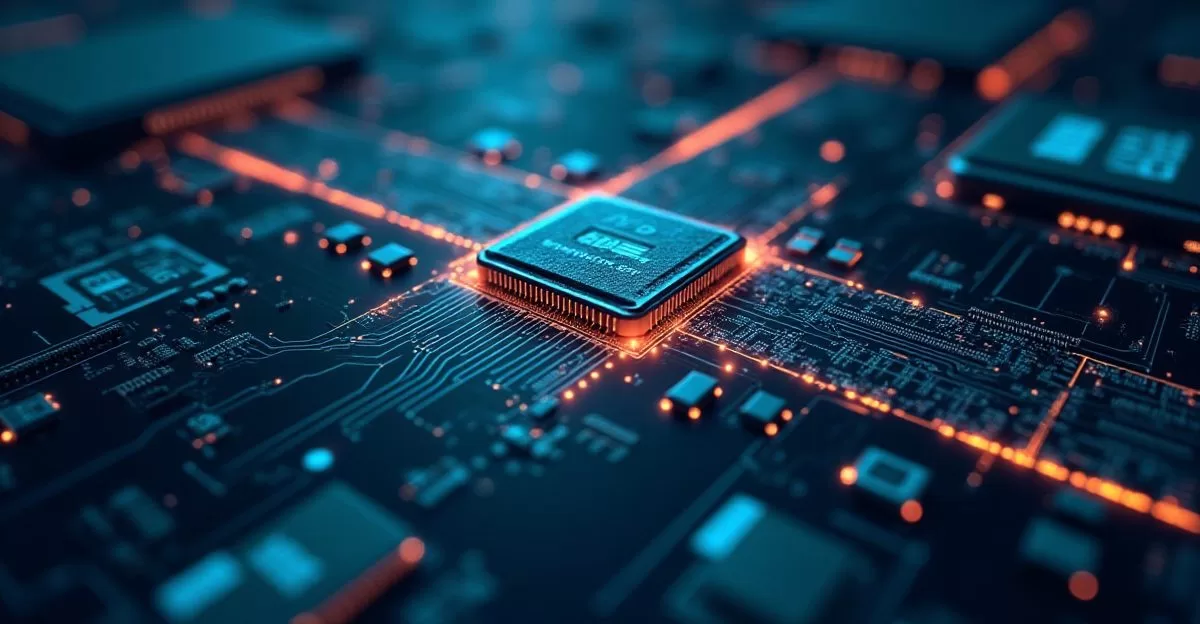4K動画をローカル生成という分かりやすい成果の裏側で、
派手さも話題性もない最適化が、静かに積み重ねられていた。
それらは直接金にならないが、確実にユーザーの負担を減らす改良だった。
第1章:なぜ今回は、NVIDIAを評価せざるを得なかったのか
NVIDIAにせよ、OpenAIにせよ、Microsoftにせよ、巨大な資本と影響力を持つ企業は、意識的に距離を取って見るべき存在だと思っている。市場を席巻する者は、構造的に世界を歪める。だからこそ批判は必要だし、私自身、その立場で書いてきた。
だが、今回のCESにおけるNVIDIAの発表群を前にして、その姿勢をいったん脇に置かざるを得なかった。理由は単純だ。文句をつける筋が、ほとんど見当たらなかったからである。
世間の関心は「ローカルでの4K動画生成」に集まっている。確かに派手で分かりやすい。しかし、それは結果に過ぎない。本質は、その裏側で積み重ねられた最適化の数々だ。PyTorch全体のスループット改善、VRAM使用量の大幅削減、既存ツールへの地味な統合。どれも見栄えはしないし、直接金になる話でもない。
それでも、それらは確実にユーザーを助ける。現場の摩擦を減らし、無駄を削り、選択肢を広げる。派手な新製品よりも、こうした改善の方が、長く効くことを私は知っている。
今回は、珍しく素直に褒める回だ。
4K動画生成に話題をさらわれがちなこのCESだが、あえてそこから視線を外し、「金にならないが、誠実な努力」がどれほどの意味を持つのかを、静かに書いていこうと思う。
第2章:CESで発表された「金にならない改善」一覧

今回のCESでNVIDIAが提示した内容を、評価や感想を挟まずに並べてみる。
・PyTorch-CUDA 最適化により、SparkにおけるAI処理性能は最大2.6倍向上
・画像・動画生成ワークロードにおいて、VRAM使用量を最大60%削減
・PyTorch 全体のスループット改善
・ComfyUI へのネイティブNVFP4/FP8精度サポート
・RTX Video超解像度の統合による4K動画生成パイプラインの高速化
・オープンモデル向けNVFP8最適化(LTX-2)
・Blenderの3Dシーンを用いた制御型動画生成パイプライン
・Ollama および llama.cpp におけるSLM推論性能の最大35%向上
盛りだくさんだが、どれも単体で見れば地味だ。
新しいGPUでもなければ、桁違いのパラメータ数を誇るモデルでもない。プレゼン映えする数字も少ない。だが、これらには共通点がある。
すべてが「既存の何かを速くする」「無駄を減らす」「使い勝手を良くする」方向を向いていることだ。新しい市場を煽る話ではなく、今すでに使われている環境の摩擦を削る作業ばかりである。
こうした改善は、マーケティング資料にしづらい。比較表に載せても響きにくいし、SNSで拡散されることも少ない。だが、日々ツールを使っている人間にとっては、確実に効いてくる。
この章では、あえて評価を下さない。
次章以降で掘り下げるが、まずはこの「並び」そのものが、今回のCESにおけるNVIDIAの姿勢を物語っている。
第3章:AI電力危機の象徴にされたNVIDIAという誤解
近年、「AI電力危機」という言葉が半ば常套句のように使われるようになった。その象徴として名指しされるのが、しばしばNVIDIAである。巨大GPU、膨大な演算、爆発的な消費電力。イメージとしては分かりやすい。
だが、今回のCESで示された一連の最適化を見ていると、NVIDIA自身はその構図を別の角度から整理し直そうとしているように見える。問題の本質は「GPUが電力を食うこと」そのものではなく、HBMを前提としたメモリ設計が、電力とコストの両面で支配的になりすぎたことにある、という整理だ。
HBMは高速である代わりに、常時大きな電力を消費する。帯域を確保するためにはスタックを積み、積めば積むほど電力も発熱も増える。この前提の上に巨大モデルを載せれば、電力消費が跳ね上がるのは当然だ。だが、それは「AIだから」ではなく、「その構成を選んだから」起きている現象でもある。
今回の発表で目立つのは、演算精度の見直し、メモリ使用量の削減、既存フレームワーク全体のスループット改善といった、HBM依存を緩める方向の努力が一貫している点だ。FP8やFP4といった低精度の活用は、単なる速度競争ではなく、電力密度そのものを下げるための手段でもある。
つまり、NVIDIAは声高に反論する代わりに、設計と最適化でこう示している。
「電力を食っているのはAIという概念ではない。
特定の前提条件に依存した構成だ。」
それを証明するために選ばれたのが、派手な新製品ではなく、地味な改善の積み重ねだった、という見方はあながち的外れではないだろう。
第4章:PyTorch“全体”を最適化するという異常な選択
今回のCESで最も評価すべき点を一つ挙げるなら、私は迷わず PyTorch 全体に手を入れたことを挙げる。
特定のモデルを速くする。
特定のデモを派手に見せる。
それは誰でもやるし、分かりやすい。だがNVIDIAが選んだのは、もっと地味で、もっと面倒で、そして圧倒的に報われにくい道だった。
PyTorchは単なるライブラリではない。研究用途から商用サービス、画像生成から動画生成、SLMから巨大モデルまで、あらゆるワークロードが雑多に流れ込む“公共インフラ”だ。ここを最適化するということは、特定の勝者を作るのではなく、全員を少しずつ楽にするという選択でもある。
妄想だが、例えばこういう場面を考えてみよう。
ある開発者がComfyUIで動画生成を回している。モデルは軽量化され、FP8で動作しているが、実際のボトルネックは推論そのものではなく、テンソルの再配置や一時バッファの確保にある。GPUの演算器は空いているのに、メモリ周りの都合で待たされる。こうした“細かい待ち時間”は、モデル側をいくら工夫しても消えない。
もしPyTorch側で、
・テンソルのライフタイム管理が改善され
・不要なアロケーションが減り
・CUDAカーネル呼び出しの粒度が見直され
・低精度演算が前提として自然に扱われる
ようになったらどうなるか。
モデルを書き換えなくても、スクリプトを触らなくても、同じコードがそのまま速くなる。
これは魔法ではない。ただの地道な最適化だ。そして、この“何も変えていないのに速くなった”という体験は、使う側にとって極めて価値が高い。
別の妄想もある。
SLMをOllamaで回しているユーザーがいる。GPU使用率は低く、VRAMも余っている。それでもレスポンスがもたつく。原因を突き詰めると、モデル本体ではなく、PyTorch内部の演算パスが低精度前提になっておらず、余計な変換が挟まっている。ここに手が入れば、SLMは“何もしなくても”軽くなる。
こうした改善は、個別の最適化記事にはならない。ベンチマークグラフも派手に跳ねない。だが、積み重なると効く。そして何より、NVIDIA自身が主役にならない。
PyTorch全体を最適化するという行為は、CUDA時代から続くNVIDIAの文化を思い出させる。前に出るのではなく、下を固める。目立つのではなく、効かせる。今回のCESで見えたのは、まさにその姿勢だった。
第5章:VRAM削減が意味する「HBMからの距離」
今回のCESで繰り返し示された「VRAM使用量の削減」という数字は、一見すると地味だ。最大60%削減と言われても、GPUの世代が一つ進んだわけでもなければ、魔法のような新技術が登場したわけでもない。
だが、この数字が示している方向性は明確だ。
それは、HBMを前提にした設計から、意識的に距離を取ろうとしているという意思表示である。
HBMは速い。疑いようがない。巨大モデルを一気に流し込むには、今なお最強の選択肢だ。しかし同時に、高価で、供給が不安定で、そして電力を食う。スタックを積み、帯域を稼ぐほど、消費電力と発熱は確実に増えていく。
これまでのAIインフラは、「HBMをどれだけ積めるか」という一点に引っ張られてきた。モデルが巨大化すればHBMを足し、帯域が足りなければさらに積む。その結果、電力問題やコスト問題が「AIの宿命」のように語られるようになった。
だが、今回の発表を冷静に見ると、NVIDIAは別の問いを立てているように見える。
本当に、そのHBMは必要か。
本当に、その精度は要るのか。
本当に、その一時バッファは保持する意味があるのか。
FP8やFP4の活用、PyTorch側のメモリ管理改善、VRAM使用量の削減。これらはすべて、「HBMに頼らなくても回る構成」を少しずつ現実に近づける作業だ。性能を落とさずにメモリを減らすという発想自体が、これまでの拡張路線とは真逆にある。
妄想を一つ挙げるなら、こういう未来だ。
同じモデル、同じプロンプト、同じワークロード。
以前は「HBM 80GBがないと無理」と言われていた処理が、最適化の積み重ねによって「大容量VRAM+UMA」で現実的に回るようになる。処理時間は少し長いかもしれないが、電力は下がり、コストは抑えられ、選択肢は広がる。
これはスパコンの話ではない。
個人や小規模チームの現実的な運用の話だ。
VRAM削減という数字は、その入口に過ぎない。NVIDIAは声高に「HBMから脱却する」とは言わない。だが、設計と最適化を通じて、静かにこう伝えている。
「HBMに全てを預けなくても、AIは成立する。」
それを証明するために選ばれたのが、派手な新GPUではなく、誰もが使っている既存環境の地道な改善だったのだろう。
第6章:ComfyUI・Blender・Ollamaを選んだ理由
今回のCESで印象的だったのは、NVIDIAが「自分たちを主役にしよう」としていない点だった。新しい統合環境を立ち上げるでもなく、独自UIを前面に出すでもない。代わりに選ばれたのは、すでに現場で使われているツール群だった。
ComfyUI、Blender、そしてOllama。
いずれも派手ではないが、実務や制作の現場で確実に根を張っている存在だ。
この選択は偶然ではない。
NVIDIAは今回、「新しい正解」を押し付けることを避けている。代わりに、「すでに選ばれている現場」に最適化を流し込むというやり方を取った。
ComfyUIに対しては、後付けのアクセラレーターではなく、低精度演算を前提としたネイティブ対応を入れる。Blenderには、生成AIを偶然の産物にしないための制御信号としての役割を与える。Ollamaやllama.cppには、SLMが“軽くて速い”という本来の価値を取り戻させる。
どれも共通しているのは、「使い方を変えさせない」ことだ。
ユーザーに新しい思想を学ばせるのではなく、今のやり方がそのまま少し楽になる方向に寄せている。
この態度は、マーケティング的には損をする。自社の存在感は薄まるし、「NVIDIAでなければならない理由」も見えにくくなる。だが、その代わりに得られるものがある。それは、現場からの信頼だ。
例えば、こういう光景だ。
ある制作者は、いつものようにBlenderでシーンを組み、ComfyUIで生成を回し、必要に応じてOllamaで補助的な推論を走らせる。特別な設定は何もしていない。だが、以前よりも落ちにくく、速く、メモリに余裕がある。それだけで、作業は確実に前に進む。
この「何も変わっていないのに、楽になった」という感覚は、最適化が最もうまく効いた証拠でもある。
NVIDIAは今回、前に出ることを選ばなかった。
主役にならず、黒衣に徹し、既存の舞台装置を少しだけ良くする。その選択は、巨大企業の振る舞いとしては、むしろ異質だ。
だが、その異質さこそが、今回のCESで最も評価すべき点なのだと思う。
第7章:カノープスの記憶──ドライバで別物にするという文化
今回のCESにおけるNVIDIAの姿勢を見ていて、個人的に強く思い出した名前がある。
カノープスだ。
同じチップを使っているはずなのに、出てくる映像は別物だった。スペック表を見れば大差はない。だが、実際に触ると分かる。画が違う。安定性が違う。信頼感が違う。その差を生んでいたのは、ハードウェアそのものではなく、ドライバと最適化だった。
当時のカノープスは、派手な数字を誇らなかった。代わりに、「この条件なら崩れない」「この設定なら事故らない」という地味な安心感を積み重ねていた。それは玄人にしか伝わらない価値だったが、一度体験すると戻れない。
今回のNVIDIAの動きには、その空気がある。
新しいGPUで殴らない。
巨大モデルで圧倒しない。
代わりに、既存環境の下に潜り込み、誰も見ない部分を磨く。
PyTorch全体の最適化、VRAM削減、低精度前提の設計、既存ツールへの静かな統合。どれも「同じチップを別物にする」仕事だ。カタログには載らないが、使えば分かる差を作る。
この種の仕事は、評価されにくい。レビュー記事では触れられないし、SNSでバズることもない。だが、長く使われる道具は、例外なくここに力を注いできた。
NVIDIAは今、GPUメーカーというよりも、環境そのものを調律する存在に近づいているように見える。前に立って指揮を執るのではなく、舞台裏で音程を合わせる役だ。
かつて、ドライバひとつで評価をひっくり返した企業があった。
そして今、似た匂いのする仕事を、世界最大級の半導体企業がやっている。
それが、今回のCESで私が感じた、一番の既視感だった。
終章:それでも、この力の使い方は評価したい
もちろん、今回のNVIDIAの振る舞いを、聖人君子のそれだと捉える気はない。
NVIDIAは営利企業であり、戦っている。そこに迷いはない。
HBMに供給も価格も頭を押さえられ、市場の伸びが構造的に制限されていることへの苛立ち。
「AI電力危機」という言葉が、あたかも自社のGPU設計そのものの罪であるかのように語られる風潮への反証。
そして、AI分野で後を追う勢力に向けた、「CUDAは簡単に追いつける代物ではない」という無言の誇示。
今回のCESに並んだ最適化の数々は、そうした複数の思惑が重なった結果だろう。
善意だけで説明できるほど、話は単純ではない。
だが、それでも評価すべき点がある。
その力が向けられた先が、ユーザーだったことだ。
市場支配を誇示するために、さらに巨大なGPUを出すこともできた。
競合を突き放すために、独自環境で囲い込むこともできた。
だが、実際に選ばれたのは、PyTorch全体の最適化であり、VRAM削減であり、既存ツールの静かな底上げだった。
これは権威の示し方としては、かなり回りくどい。
だが同時に、「使われ続ける基盤」を誰よりも理解している者の選択でもある。
力を持つ企業が、その力をどこに使うか。
今回のNVIDIAは、少なくとも「ユーザーの不満が溜まっている場所」に金と人を投じた。
そこは手放しに評価していい。
動機が混ざっていようと、計算があろうと、結果として現場が楽になるなら、それは正しい力の使い方だ。
このCESで示されたのは、善意ではなく、成熟した自信と苛立ちが同居する現実的な強さだった。
そして、その強さがユーザーのほうを向いていたことを、私は素直に評価したい。