AMDのROCm 7.1.1が、ついにWindows環境へ本格的に降りてきた。
しかも今回は、研究用途や実験的サポートではない。生成AI制作の現場で広く使われているComfyUIが、公式Windows版インストーラにおいてROCm 7.1.1をネイティブに採用した。
これにより、Windows上で「CUDAを前提としない」生成AI制作フローが、初めて現実的な選択肢となった。
NVIDIAのCUDAが長年支配してきたGPU計算の世界に、AMDはGPU単体ではなく、CPUと大容量メモリを含めたPC全体の設計思想で切り込んでいる。
本記事では、ROCm 7.1.1とComfyUI公式対応が持つ意味、CUDA一強体制に生じた“現実の穴”、そしてAMDが見据える生成AIの次の主戦場を整理していく。
CUDAは、長いあいだGPU計算の「事実上の憲法」だった。
NVIDIA製GPUを使う限り、CUDAに従うことは選択ではなく前提であり、研究も開発も生成AIも、その支配構造の上に築かれてきた。
AMDにも対抗軸はあった。OpenCL、Vulkan、そしてROCm。
だがそれらは多くの場合、「理屈は正しいが現場で使いにくい」存在にとどまり、CUDA一強の構図を崩すには至らなかった。特にWindows環境では、ROCmは長らく“Linux前提の実験場”という位置づけを抜け出せずにいた。
その空気が、静かに変わり始めている。
AMDはROCm 7.1.1をもって、Windows上の生成AI制作フローへ本格的に踏み込んできた。
しかも切り込み方は、研究者向けのAPIやベンチマークではない。ComfyUIという、現場で実際に使われている生成AIの制作導線を正面から押さえに来たのだ。
ワンクリックで動くComfyUI Desktop。
その裏側でROCmが選択肢として“普通に存在する”世界。
これは「AMDが速くなった」という話ではない。
CUDAの牙城に、初めて“現実的な穴”が開いたという話だ。
本記事では、ROCm 7.1.1がWindowsに降りてきた意味、ComfyUI公式対応が持つ戦略的な重み、そしてそれがCUDA一強体制に与える影響を、冷静に、しかし楽観も悲観もせずに見ていく。
ROCmは覇権を奪うのか。
それとも、もう一つの「使える選択肢」になるのか。
少なくとも今は、無視できない地点まで来ている。
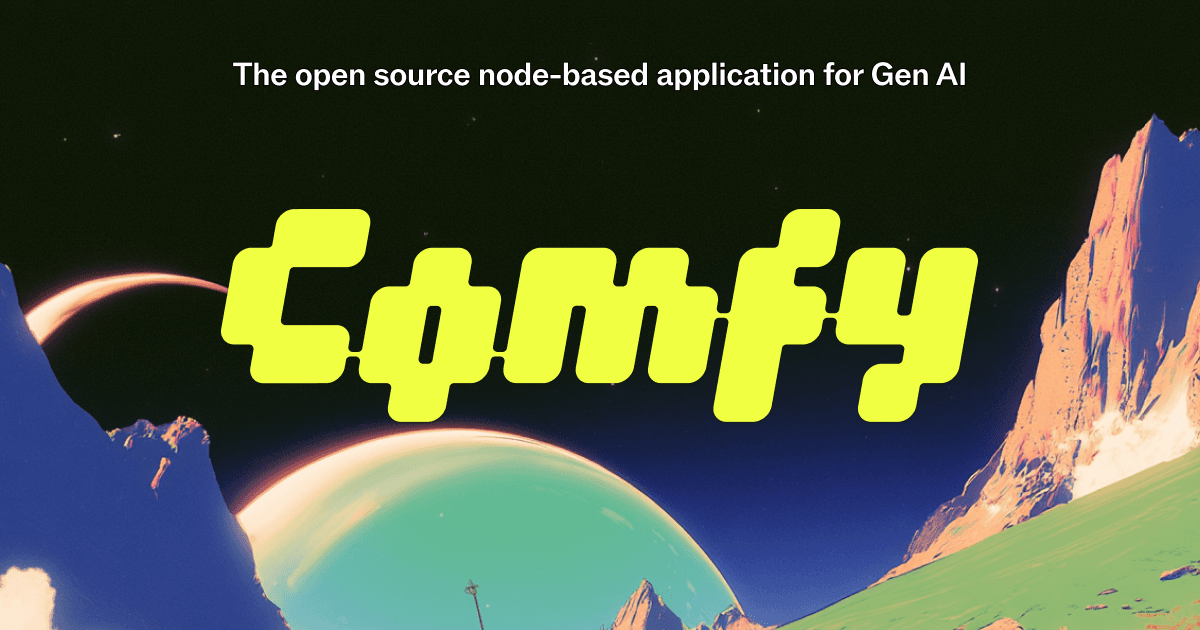
第1章 なぜ「ComfyUI」だったのか
ROCm 7.1.1のWindows対応で、AMDが最初に押さえに行った相手は、Stable Diffusionでも、PyTorch単体でもなかった。
選ばれたのは ComfyUI —— 生成AIの“制作現場”そのものだ。
これは偶然ではない。
ComfyUIは、生成AIを「試す道具」ではなく、「組み立てて使う道具」として扱う数少ないUIだ。
ノードベースでパイプラインを可視化し、モデル・LoRA・VAE・Sampler・ControlNet・後処理までを一つの制作工程として管理する。そこでは、単発の推論速度よりも、反復性・安定性・メモリの扱いやすさが重視される。
CUDAが強かったのは、研究と推論の世界だ。
だが制作の現場では、話が少し違う。
ComfyUIは、巨大なVRAMを前提にしない。
必要なのは「速さ」よりも、「落ちないこと」と「組み替えられること」だ。
その性質は、大容量のシステムメモリを柔軟に使えるROCmの思想と相性がいい。
AMDがComfyUIを選んだのではない。
ComfyUIが、ROCmを受け入れられる数少ない制作フローだったと言ったほうが正確だ。
もう一つ重要なのは、ComfyUIが現場主導で進化してきた点だ。
特定ベンダーの最適化よりも、「とりあえず動く」「自分で直せる」「ワークフローを共有できる」ことが優先される文化。
その文化圏に、ROCm 7.1.1が“公式に”入り込んだ意味は小さくない。
Windows版ComfyUIの公式インストーラは、CUDAの存在を前提にしていない。
依存関係の解決から実行環境まで、ROCm 7.1.1が最初から選択肢として組み込まれている。
これは「AMD対応しました」というレベルの話ではない。
CUDA以外でも“普通に始められる生成AI制作環境”を、初めてWindowsで提示したということだ。
CUDA一強が揺らぐとすれば、研究室からではない。
まず崩れるのは、こうした制作フローの入口だ。
ComfyUIは、派手なベンチマークを出さない。
だが、日々回される無数のワークフローの中で、「CUDAじゃなくても困らない」という感覚を静かに積み上げていく。
ROCm 7.1.1とComfyUI公式対応は、その第一歩に過ぎない。
だが、現場で使われる導線を押さえたという一点において、これまでのROCmとは明確に違う。
CUDAが見落としていた盲点
NVIDIAにあって、AMDにないもの。
それはCUDAだ。
だが逆に言えば、NVIDIAになくて、AMDにあるものもある。
それがCPUだ。
CUDAは、GPUを中心に世界を組み立ててきた。
計算も最適化も、そして価値の源泉もGPUに集約する思想。
巨大なVRAM、巨大なカード、巨大な電力。
その前提の上で、生成AIの進化は語られてきた。
だが、PCという現実のプラットフォームを見渡したとき、
世界で最も数が多く、最も安定して供給され、
そして最も柔軟に進化している計算資源は何か。
答えはCPUだ。
AMDはその事実から目を逸らさなかった。
GPUでCUDAを真似るのではなく、CPUとGPUを一体の計算資源として再定義する。
大容量のシステムメモリを前提に、UMAやVGMでGPUに食わせる。
「VRAMを積め」ではなく、「メモリを積め」という発想。
これはCUDAの思想圏には、ほとんど存在しなかった視点だ。
世界のPC市場では、AMD製CPUの存在感が年々増している。
デスクトップ、ノート、ワークステーション、そしてエッジ。
GPUは高価でも、CPUとメモリは比較的自由に構成できる。
その現実を踏まえれば、CPUを起点に生成AIの導線を引き直すという判断は、極めて合理的だった。
ROCm 7.1.1とComfyUI公式対応は、
GPU覇権を奪うための奇襲ではない。
「GPUだけで世界を回す」という前提そのものを揺さぶる一手だ。
CUDAは速い。
だがCUDAは、PCという存在を十分に見ていなかった。
AMDが見出した活路は、そこにある。
第2章 Windowsで「普通に使える」ことの意味
ROCmがWindowsに来た、という事実そのものよりも重要なのは、
「Windowsで“普通に使える”状態まで降りてきた」という点だ。
これは技術者ほど軽視しがちだが、現実の分水嶺はいつもここにある。
これまでROCmは、正しかった。
設計も思想も、CUDAに対する対抗軸として一貫していた。
だがその多くは、Linuxという“選ばれた環境”の上で語られてきた。
Docker、依存関係、ドライバ整合性──
それらを乗り越えられる人にとっては問題ではなくても、
制作現場の大多数にとっては入口以前で脱落する壁だった。
Windowsは違う。
良くも悪くも、生成AIの“現場”はWindowsにある。
- クリエイター
- デザイナー
- 動画編集
- 生成画像の試行錯誤
- 業務PCの延長線でのローカルAI活用
これらの多くは、LinuxではなくWindows上で回っている。
だからこそCUDAは強かった。
「Windowsでそのまま動く」こと自体が、最大の武器だったからだ。
今回、ComfyUIの公式Windows .exeインストーラが示したのは、
ROCmがついにその土俵に上がった、という事実だ。
依存関係を自分で解決する必要はない。
Python環境を整える必要もない。
CUDAを入れるかどうかで悩む必要すらない。
ダウンロードして、起動する。
その結果、裏側でROCm 7.1.1が選択される。
この「意識しなくていい」という体験は、想像以上に強い。
CUDAは、選ばれてきた。
ROCmは、これまで“選ばせようとしていた”。
だが今回のComfyUI公式対応では、
ROCmは最初からそこにある選択肢になった。
これは覇権争いではない。
慣性の奪い合いだ。
一度「CUDAじゃなくても普通に回る」体験をした制作フローは、
次からも同じ構成を選ぶ。
理由がなければ、わざわざ戻らない。
ROCm 7.1.1がWindowsで“普通に使える”ようになったこと。
それは、CUDAの牙城を正面から殴る話ではない。
現場の手癖を、静かに書き換えにきたという話だ。
第3章 性能の話をしていいライン/してはいけないライン
ROCm 7.1.1の話題になると、どうしても数字が先に踊る。
「最大5.4倍の性能向上」。
AMD自身もそう書いているし、見出しとしては強い。
だが、この数字をそのまま信じる人と、
最初から信じない人のどちらも、少し危うい。
まず、言っていいことから整理しよう。
ROCm 6.4から7.1.1への改善は、実在する。
カーネル実装、メモリ管理、混合精度(FP16 / BF16 / FP8)の扱い、
そしてComfyUIのようなワークフロー型UIとの相性。
これらが積み重なって、特定条件下では体感差が出るのは事実だ。
特に差が出やすいのは、
- VRAMに収まりきらないモデル構成
- LoRAやControlNetを重ねた複雑なワークフロー
- 長時間の反復生成
- GPUとCPUのメモリ往復が多いケース
ここでは、ROCmの「大容量システムメモリを前提にした設計」が効いてくる。
CUDAがVRAM内完結を美徳としてきたのに対し、
ROCmはCPUとGPUをまたぐ現実的な運用を最初から受け入れている。
だから、速くなる場面は確かにある。
一方で、言ってはいけないラインもはっきりしている。
ROCm 7.1.1は、CUDAを全面的に上回ったわけではない。
VRAMが潤沢にある環境、単純な推論ベンチマーク、
GPU単体で閉じた処理では、CUDAが依然として強い。
また、Windows環境では、
- 対応GPUが限定される
- プレビュー的なドライバが前提になる
- メモリ容量が足りないと不安定になりやすい
- 32GB構成では現実的でないケースも多い
といった制約も残っている。
だから、この話を
「AMDのほうが速い」
「CUDAはもう終わり」
とまとめるのは、完全に間違いだ。
ここで評価すべきなのは、絶対性能ではない。
ROCm 7.1.1が示したのは、
- CUDAでなければ成立しない、という前提が崩れたこと
- Windows上の制作フローで、選択肢として成立したこと
- 性能の話を“比較”ではなく“用途”で語れる地点に来たこと
つまり、性能は勝敗の話ではなく、適合の話になった。
生成AIの現場では、
「一番速い」よりも
「落ちない」「回し続けられる」「構成を変えられる」
ほうが価値を持つ。
ROCm 7.1.1は、そこで初めて評価対象に入った。
この章の結論はシンプルだ。
数字は盛れる。
だが、本当に意味があるのは、
数字を盛らなくても使う理由が生まれたことだ。
第4章 制約と現実──ROCmは「誰向け」なのか
ここまで読んで、「じゃあ自分もROCmに乗り換えるべきか?」と考え始めた人がいるなら、
一度、足を止めて現実を整理しておいたほうがいい。
ROCm 7.1.1は、確かに“使える選択肢”になった。
だが、それは誰にでも無条件に開かれた道という意味ではない。
まず、ハードウェアの現実がある。
Windows版ComfyUIの公式インストーラが前提としているのは、
大容量メモリ環境だ。
64GB、できれば128GB。
これは推奨というより、思想の前提条件に近い。
32GB環境でも動かないわけではない。
だが、複雑なワークフローや大きめのモデルを扱い始めた瞬間、
「不安定」「遅い」「落ちる」という体験に直結しやすい。
ROCmはVRAM不足を“根性で回避する魔法”ではない。
システムメモリを計画的に使う設計だ。
そこを誤解すると、期待外れに終わる。
次に、ソフトウェアとドライバの成熟度。
ROCm 7.1.1は、Windowsではまだ若い。
公式に用意されたルートとはいえ、
ドライバはプレビュー的な性格を残しているし、
環境によっては細かな癖に遭遇する。
CUDAのように「何も考えずに入れて終わり」という段階ではない。
トラブルが起きたとき、
「仕組みを理解して自分で戻れる」人のほうが向いている。
では、ROCmは誰向けなのか。
答えは意外と限定的だ。
- 生成AIを制作フローとして使っている人
- ワークフローを組み替えながら反復する人
- GPU性能よりも、構成の自由度とメモリ容量を重視する人
- CUDA一択である必要性に、うっすら疑問を持っている人
逆に言えば、
- ベンチマーク至上主義の人
- 最新GPUを毎世代追いかける人
- 単一モデルを最速で回したい人
こうした層にとって、ROCmは今も最適解ではない。
だが、それでいい。
ROCm 7.1.1の価値は、
CUDAを置き換えることではなく、
CUDA以外を選んでも成立する場所を作ったことにある。
制約があるからこそ、
誰のための技術なのかがはっきりする。
ROCmは、万人向けになろうとしていない。
だからこそ、現場で静かに根を張り始めている。
第5章 これは覇権争いではない
ROCm 7.1.1とComfyUI公式対応の話題は、どうしても
「CUDA vs ROCm」
「NVIDIA vs AMD」
という構図に引き寄せられがちだ。
だが、この出来事を覇権争いとして理解すると、
ほぼ確実に本質を見誤る。
AMDは、CUDAを倒しに来たわけではない。
正面衝突を仕掛けるには、CUDAはあまりにも巨大で、
そしてあまりにも深くエコシステムに根を張っている。
今回AMDがやったことは、もっと地味で、もっと現実的だ。
CUDAが前提でなくても、生成AIの制作フローが成立する場所を一つ作った。
それだけだ。
だが、この「それだけ」は、思っている以上に重い。
覇権というのは、性能やシェアの数字で決まるものではない。
「選ばれなくても困らない」状態になった瞬間に、初めて揺らぎ始める。
CUDAは、長いあいだ
「速いから使われている」のではなく、
「他に現実的な選択肢がなかったから使われていた」。
ROCm 7.1.1とComfyUI公式対応が突き崩したのは、そこだ。
選択肢が増えた世界では、人は必ず合理化を始める。
コスト、構成、電力、メモリ、将来の拡張性。
そのすべてをGPU一枚に集約する必要があるのか、と。
AMDはGPUで勝とうとしていない。
PCという“全体”で勝ち筋を作ろうとしている。
CPU、メモリ、GPU、OS。
その全部を含んだ設計思想こそが、ROCmの正体だ。
だからこれは、短距離走ではない。
5年、10年単位で効いてくる、静かな布石だ。
終章 ROCmが開けた「現実の穴」
ROCm 7.1.1がWindowsに降りてきた。
ComfyUIが公式にそれを受け入れた。
この二つが重なったことで、
CUDA一強の壁に、初めて現実的に通れる穴が開いた。
それは大きな破壊ではない。
劇的な革命でもない。
ただ、
「CUDAじゃなくても、困らなかった」
という体験が、確かに生まれた。
生成AIの世界では、この種の体験が最も強い。
一度でも成立してしまえば、
次からは「それでいい理由」を探し始めるからだ。
AMDの狙いは、GPUを売ることではない。
CPUとメモリを含めた、PC全体の価値を再定義すること。
生成AIを、特別な計算機から
日常的な制作環境へ引き戻すことだ。
メモリ価格の高騰という逆風はある。
ROCmはまだ万人向けではない。
CUDAは今も最強だ。
それでも、この一歩は消えない。
ROCm 7.1.1とComfyUI公式対応は、
「いつか起きるかもしれない未来」ではなく、
もう起きてしまった現実だ。
CUDAの時代が終わるかどうかは、まだ分からない。
だが、CUDAだけの時代は、確実に終わり始めた。
それで十分だ。


